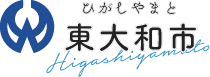後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度の運営主体
後期高齢者医療制度は、都内62の全区市町村が加入する「東京都後期高齢者医療広域連合」(以下、広域連合という)が運営しています。市は広域連合と連携し、申請などの窓口業務、保険料の徴収業務や相談業務を行います。
後期高齢者医療制度の被保険者
75歳以上の方
それまで加入していた医療制度(国保、健康保険、共済など)に関係なく、75歳の誕生日から被保険者となります。
加入のための手続は必要ありません。
65歳から74歳までの方で一定の障害のある方
市において申請し、広域連合の認定(障害認定)を受けた日から被保険者となります。
後期高齢者医療制度の給付と一部負担金の割合
後期高齢者医療制度では、現物給付(医療サービスの提供)と現金給付(医療費の支給)を行います。また、医療機関などで受診する際に窓口で支払う医療費の一部負担金(自己負担)の割合は「1割」・「2割」・「3割」のいずれかです(一部負担金の割合は毎年8月1日に所得等をもとに判定されます。)。
後期高齢者医療制度の資格確認書
資格確認書の交付
令和6年12月2日以降、被保険者証は新たに交付されることがなくなり、マイナ保険証の保有状況に応じて資格確認書もしくは資格情報のお知らせが交付されるようになりました。後期高齢者医療制度では、暫定的な運用として、令和8年7月31日までマイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付しています。
資格確認書は、新たに75歳になられる方や、転居等で券面情報が変更となる方にお送りします。
診察を受けるときは、マイナ保険証か資格確認書を必ず医療機関等に提示してください。
資格喪失後や一部負担金の割合が変更となった後に古い資格確認書をお使いになると、医療費の納付や払い戻しの手続が必要となる場合がありますので、必ず新しい資格確認書をご利用ください。
資格確認書の再交付
資格確認書を紛失したり、破損したときには再交付手続が可能です。手続完了後は10日以内に郵送します。なお、即日交付する場合は、写真付の公的身分証明書等(マイナンバーカード、運転免許証又はパスポート等)が必要となります。
資格確認書の返還
都外への転出や生活保護の開始等により、被保険者の資格を喪失したときは、転出手続等の所定の手続を経た上で、資格確認書を保険年金課にお返しください。
後期高齢者医療制度の財政と保険料
後期高齢者医療制度の財政は、被保険者の皆さんに納めていただく保険料(約1割)と、現役世代からの支援金(約4割)、そして国・都・市区町村による公費(約5割)で運営されています。
後期高齢者医療制度の保険料は、均等割額と所得割額の合計額を被保険者一人ひとりに納めていただきます。
保険料率は2年ごとに見直され、東京都内で均一です。
令和6・7年度の東京都の保険料額[限度額80万円](※1)
- 均等割額
- 被保険者1人当たり 47,300円
- 所得割額
- 賦課のもととなる所得金額(※2)×9.67%(※3)
※1 次の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。
(1)昭和24年3月31日以前に生まれた方
(2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)
※2 賦課のもととなる所得金額とは、旧ただし書き所得のことで、前年の総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した額です。なお、所得金額等により保険料の均等割額、所得割額が軽減される場合があります。
※3 令和6年度の所得割の率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%となります。なお、令和7年度は全ての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。
所得変更・資格喪失等による保険料額の変更
所得の変更(修正申告等)がある方、又は転出や死亡により資格喪失等のある方は、事務処理上の都合により保険料額決定通知書の反映には間に合わず、保険料額が変更されていない場合があります。
この場合には、改めて保険料額を変更した保険料額変更決定通知書をお送りいたします。
保険料を納めすぎた方への還付金
納付した額について、保険料額の変更等により差額が生じた場合は、後日、還付に関する請求書をお送りいたします。
保険料の納め方
保険料の納付方法は原則として介護保険料と同じ公的年金からの引き落としとなります(特別徴収)。年金からの引き落としの対象とならない方は、納付書または口座振替で納めていただきます(普通徴収)。
特別徴収(年金からの天引き)
保険料は原則として、公的年金から年6回天引きされます。
下記要件を全て満たした時は自動的に特別徴収に切り替わります。
- 特別徴収の対象となる年金(老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金)を受給しており、受給額が年18万円以上の方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超えない方
- 介護保険料が年金からの天引き(特別徴収)となっている方
※特別徴収の対象となる方でも、年度途中で新たに資格を取得した方(75歳になった方等)や、他の市町村から転入した方は、一定期間普通徴収(納付書または口座振替)となります。
※特別徴収でお支払いいただく方のうち、希望される方は、手続をすることにより保険料を口座振替に変更することができます。事前に金融機関の窓口にて保険料の口座振替の手続を行っていただいた上、「ご本人控え」をお持ちになって保険年金課の窓口へお申し出ください。
特別徴収における仮徴収と本徴収
各年度の保険料は7月に決定するため、特別徴収においては、仮徴収と本徴収により納めていただきます。
仮徴収
4月、6月、8月の特別徴収は、前年度2月の特別徴収額と同額になります。
本徴収
本徴収は、7月に決定を行います。先に納めていただいた仮徴収額を引いた残りの金額が10月、12月、2月の特別徴収額となります。
普通徴収
次に該当する方は普通徴収となります。納期は、毎年7月から2月までの計8期となります。納付書または口座振替で納付願います。
- 公的年金の受給額が年額18万円未満の方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方
- 新たに後期高齢者医療制度の対象となった方
- 年度途中で転入した方
- 介護保険料が年金からの天引き(特別徴収)になっていない方
納付取扱場所
納付書による場合は、次の金融機関、東大和市清原市民センターまたはコンビニエンスストアで納められます。
金融機関
りそな銀行、りそな銀行派出所(市役所内)、みずほ銀行、埼玉りそな銀行、きらぼし銀行、山梨中央銀行、東和銀行、飯能信用金庫、西武信用金庫、青梅信用金庫、多摩信用金庫、大東京信用組合、中央労働金庫、東京みどり農業協同組合の各支店、東京都信用農業協同組合連合会、ゆうちょ銀行・郵便局(東京都、山梨県及び関東各県所在。)
※納期限を過ぎると、ゆうちょ銀行及び郵便局では取り扱いできません。
東大和市清原市民センター
平日の午前8時30分から午後5時まで
コンビニエンスストア
くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セブン-イレブン、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ローソン、MMK(マルチメディアキオスク)設置店、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- 全国のお店で納付できます。
- 納付書1枚当たりの金額が30万円を超える場合は、コンビニエンスストアでは取扱いができません。金融機関等で納付してください(30万円を超える納付書には、バーコードの印字がなく、取扱いができない旨が明記されます)。
- 納付書の金額を訂正して使用することはできません。
- バーコードの印字がない納付書や、破損などでバーコードを読み取ることができない場合は、コンビニエンスストアで納付することができません。
コンビニエンスストア収納事務委託
地方自治法第243条の2第1項の規定により、東大和市後期高齢者医療保険料(普通徴収分)の収納事務を、次の指定公金事務取扱者に委託したので、地方自治法第243条の2第2項の規定に基づき公表します。
委託先
名称 株式会社NTTデータ
所在地 東京都江東区豊洲三丁目3番3号
指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入
後期高齢者医療保険料
指定公金事務取扱者に指定した日
令和7年4月1日
公金事務を委託した日
令和7年4月1日
お近くに納付場所がない時には
お近くに納付書を取り扱っている金融機関の本・支店やコンビニエンスストアがない場合は、保険年金課までご連絡ください。全国のゆうちょ銀行及び郵便局で納付できる「払込取扱票」を送付しますので、お近くのゆうちょ銀行及び郵便局で払い込んでください。
東京いきいきネットで保険料の試算ができます
東京いきいきネットのホームページで実際に被保険者の方の保険料が計算できますのでご利用ください。
健康診査を受けましょう
被保険者の健康保持増進のため、年に1回後期高齢者の健康診査を実施します(被保険者の皆様に受診券を発送します。)。
健康診査は、次のリンクをご覧ください。
届け出について
次のときは必ず届け出をしてください。
届出に必要なもの
- 転入のとき
- 負担区分証明書(東京都外から転入した場合のみ)、※1 本人確認書類
- 転出のとき
- 資格確認書、※1 本人確認書類
- 死亡したとき
-
死亡した方の資格確認書、喪主と死亡した方の両方の名前の入った領収書、喪主の印鑑(自動印以外のもの)
葬祭費の支給については、下記のリンク先「葬祭費の支給(後期高齢者)」を参照してください。
- 住所がかわったとき(市内転居等)
- 資格確認書、※1 本人確認書類
- 65歳以上で障害の認定を受け後期高齢者医療制度に加入するとき
- 資格確認書、資格情報のお知らせ、診断書または身体障害者手帳等、※1 本人確認書類
- 生活保護を受けるようになったとき、または、受けなくなったとき
- 資格確認書、※1 本人確認書類、※2生活保護受給証明書
※1 本人確認書類とは、マイナンバーカードや運転免許証などの身元確認書類です。
※2生活保護を受けるようになった時のみお持ちください。
送付先の変更について
申請方法
入院中である等の理由で書類の管理が困難である場合には、送付先を変更することが可能です。
「後期高齢者医療に関する送付物の送付先変更依頼書」を印刷し、必要事項を記載の上、ご郵送ください。
また、送付先となる方の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証等)の写しを必ずご添付ください。
申請書
詳しい内容は「東京いきいきネット」
後期高齢者医療制度のさらに詳しい内容は、東京都後期高齢者医療広域連合オフィシャルサイトのホームページ「東京いきいきネット」を参照してください。東京いきいきネットのホームページは、次のリンクをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部保険年金課高齢者医療年金係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1026) ファクス:042-563-5927
健幸福祉部保険年金課高齢者医療年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。