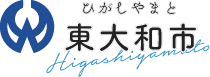児童手当
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している者に対して支給する手当です。
上記リンクをクリックすると、各タイトルまで移動します。
支給対象
東大和市内に住所を有し、高校3年生までの児童(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童)を養育している方
認定請求者
認定請求者(申請者)は、父または母のうちのいずれかで所得が高いほうの方とします。
所得が同程度の場合は、児童の扶養状況等をもとに判断します。
公務員の方
主たる生計の中心者が公務員の場合、勤務先から支給されます。
ただし、独立行政法人等にお勤めの方、出向等で公務員でなくなった方で、勤務先から支給されない場合は、市役所へ申請してください。
外国籍の方
外国籍の方は在留資格、在留期間に一定の要件があります。
次のいずれかに該当する方は対象となりません。
- 短期滞在
- 在留期間を過ぎている
その他
児童が原則として日本国内に住んでいることが要件となります。(児童の留学を除く)
児童が施設等に入所している場合、施設の設置者等へ支給します。
児童を養育している未成年後見人の方に児童手当を支給します。未成年後見人が法人である場合は、法人へ手当を支給します。
両親が離婚協議(調定)中で別居の場合は、児童と同居している方が優先されます。
次のいずれかに該当する方は申請できません。児童と同居している方が申請してください。
- 海外に単身赴任している
- 逮捕、拘禁されている
手当額(月額)
児童手当月額一覧表
児童一人あたりの手当月額
| 年齢区分 | 第1子・第2子 |
第3子以降 |
|---|---|---|
| 0歳~3歳の誕生月 |
15,000円 |
30,000円 |
|
3歳~高校生年代 |
10,000円 |
第1子・第2子・第3子以降の数え方は、「申請者が養育している0歳から大学生年代までの子」の中で出生順に数えます。
※大学生年代とは、18歳に達した日以後最初の3月31日を経過した者から、22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者です。大学生年代の子の養育については、「(1)受給者が当該子に対し日常生活上の世話や必要な保護をしていること」、「(2)当該子が受給者の収入により日常生活の全部または一部を営んでおり、これを欠くと通所の生活水準を維持できないこと」の双方に該当することです。子が就労・別居・婚姻・出産していても、申請者が上の状態のように養育していれば、子の数の対象となります。
※大学生年代の子を養育している場合、子の数の対象となるためには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。以下の(ア)~(ウ)に該当するときに市から通知を送付します。
(ア)養育している子が大学生年代を迎えるとき
(イ)「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出の際に、子が学生と記載した場合、当該子が大学生年代を終える前に卒業予定時期を迎えるとき
(ウ)「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出の際に、子が無職・その他と記載した場合、毎年6月の現況確認のとき
※大学生年代の子の養育については、受給者と同居している場合、養子縁組の有無は関係ありません。(支給対象児童については、養子縁組をしている場合に限り受給者になることが可能です。)
該当する場合は、該当子が支給対象から外れる3月に、「額改定認定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
支給月
4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回、前月までの2か月分を各4日から10日の間の金曜日に支給します。
| 4月支給 | 2、3月分 |
|---|---|
| 6月支給 | 4、5月分 |
| 8月支給 |
6、7月分 |
| 10月支給 | 8、9月分 |
| 12月支給 | 10、11月分 |
| 2月支給 | 12、1月分 |
振込みから口座に入金されるまでに日数がかかる場合があります。
振込名義は、「ジテヒガシヤマトシカイケイカンリシヤ」です。
転出等により、東大和市での受給資格が消滅した場合は、消滅した月までの手当を振込日以外に振り込む場合があります。
申請手続き
申請した月(認定請求書を東大和市が受理した日が属する月)の翌月分から手当を支給します。
ただし、出生日、転入日(前住所地に届出した転出予定日)の翌日から起算して15日以内に申請した場合、出生日、転入日等の翌月分からの支給となります。
原則として、認定申請書に必要書類を添えて提出してください。
添付書類が揃っていなくても受け付けますが、不足書類は後日速やかに提出してください。
必要な書類がすべて提出されてから、審査をします。
正当な理由なく一定期間を越えて提出がない場合は、書類不備により却下処分を行います。
審査後、認定となった場合は認定通知書を、却下となった場合は却下通知書を郵送します。
第1子の出生、または受給者が東大和市に転入した場合
申請期限
出生日、または前住所地での転出予定日の同月内に申請してください。
月末のために同じ月内での申請が難しい場合は、各事由発生日の翌日から15日以内に申請してください。
申請に必要な書類等
| 必要なもの | 備考 |
|---|---|
| 認定請求書(必須) |
窓口にあります。 印刷・郵送提出される方はA4両面で印刷してください。 マイナポータルでの申請も可能です。 |
| 申請者名義の口座がわかるもの(必須) |
申請者の口座が確認できる通帳またはキャッシュカード等 ※申請者名義以外の口座は指定できません。 ※ネット銀行等で通帳がない場合は、口座が証明できる画面の提示または口座情報をプリントアウトしたものが必要です。 |
|
申請者の健康保険加入状況が確認できるもの
|
資格確認書、マイナポータルからプリントした資格情報画面等 ※公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)において必要情報が確認できない場合(国家公務員共済または地方公務員等共済組合の組合員であるが、児童手当法上の公務員に含まれない方。共済組合や職員団体の事務を行う者、国立大学法人の職員、日本郵政共済の組合員、特定地方独立行政法人の職員等)、提出していただくことがございます。 |
|
監護相当・生計費の負担についての確認書 |
大学生年代までの子を3人以上養育し、そのなかで大学生年代の子が1人以上いる方は、額改定認定請求書に加え、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。 大学生年代の子の監護の考えにつきましては、「(1)受給者が当該子に対し日常生活上の世話や必要な保護をしていること」、 「(2)当該子が受給者の収入により日常生活の全部または一部を営んでおり、これを欠くと通所の生活水準を維持できないこと」の双方に該当することです。 子が就労・別居・婚姻・出産していても、申請者が上の状態のように養育していれば、この数の対象となります。 |
-
認定請求書 (PDF 357.2 KB)

※A4両面で印刷してください。 -
認定請求書記入例 (PDF 527.0 KB)

認定請求書の記入例です。 -
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 112.5 KB)

※子が3人以上かつ大学生年代の子がいる方のみ提出をお願いします。 -
監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例 (PDF 206.5 KB)

※監護相当・生計費の負担についての確認書の記入例です。
申請方法
(1)窓口申請 東大和市役所1階7番窓口 子育て支援課 手当・助成係
(2)郵送申請
必要書類に記入の上、必要書類を添付し、子育て支援課へご郵送ください。
受付日は、子育て支援課に到着した日となりますので、ご注意ください。
(3)電子申請
-
手続の検索・電子申請(マイナポータル)(外部リンク)

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求の電子申請はこちらから
※郵送または電子申請をする場合は、乳幼児医療費助成制度や義務教育就学児医療費助成制度の申請もれにご注意ください。
第2子以降の出生等で養育する児童が増えた場合
申請期限
養育する児童が増えた日(第2子の出生日等)の同月内に申請してください。
月末のために同じ月内での申請が難しい場合は、各事由発生日の翌日から15日以内に申請してください。
申請に必要な書類等
| 必要なもの | 備考 |
|---|---|
| 額改定認定請求書(必須) |
窓口にあります。 印刷・郵送提出される方は、A4両面で印刷してください。 |
|
申請者の健康保険加入状況が確認できるもの |
資格確認書、マイナポータルからプリントした資格情報画面等 ※公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)において必要情報が確認できない場合(国家公務員共済または地方公務員等共済組合の組合員であるが、児童手当法上の公務員に含まれない方。共済組合や職員団体の事務を行う者、国立大学法人の職員、日本郵政共済の組合員、特定地方独立行政法人の職員等)、提出していただくことがございます。 |
| ※監護相当・生計費の負担についての確認書 |
大学生年代までの子を3人以上養育し、そのなかで大学生年代の子が1人以上いる方は、額改定認定請求書に加え、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。 大学生年代の子の監護の考えにつきましては、「(1)受給者が当該子に対し日常生活上の世話や必要な保護をしていること」、 「(2)当該子が受給者の収入により日常生活の全部または一部を営んでおり、これを欠くと通所の生活水準を維持できないこと」の双方に該当することです。 子が就労・別居・婚姻・出産していても、申請者が上の状態のように養育していれば、子の数の対象となります。 |
-
額改定認定請求書 (PDF 199.9 KB)

※A4両面で印刷してください -
額改定認定請求書 記入例 (PDF 435.8 KB)

-
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 112.5 KB)

※A4両面で印刷してください。
※子が3人以上かつ大学生年代の子がいる方のみ提出をお願いします。 -
監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例 (PDF 206.5 KB)

申請方法
(1)窓口申請 東大和市役所1階7番窓口 子育て支援課 手当・助成係
(2)郵送申請
必要書類に記入の上、必要書類を添付し、子育て支援課へご郵送ください。
受付日は、子育て支援課に到着した日となりますので、ご注意ください。
(3)電子申請
-
手続の検索・電子申請(マイナポータル)(外部リンク)

児童手当等の額の改定の請求の電子申請はこちらから
下記に該当する場合は別途書類が必要です。
申請者が児童と別居している場合
仕事(単身赴任等)、学校(入寮、通学等)、親族の介護等の理由により申請者が児童と別居し、監護している場合、監護事実の確認が必要となるため、下記書類をご提出ください。
-
監護事実の同意書 (PDF 76.0 KB)

窓口にもあります。印刷する場合はA4で印刷してください。 -
監護事実の同意書記入例 (PDF 111.2 KB)

監護事実の同意書の記入例です。
公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)において必要情報が確認できない場合
| 必要なもの | 備考 |
|---|---|
|
申請者の保険証またはコピー |
年金情報が公簿により確認できない場合。 |
| 住民票原本 |
住民登録が公簿により確認できない場合。 児童の属する世帯全員の続柄記載のある住民票で、交付から3か月以内のもの。 |
| その他 | 必要に応じて追加の書類を求める場合があります。 |
医療費助成制度も併せて申請する方
-
子ども医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青)
乳幼児医療費助成制度の医療証の交付申請方法(窓口、郵送のみ)
現況届(年度更新の手続き)
現況届が必要な方について
現況届の提出は原則不要です。毎年6月1日時点の受給者の状況を公簿等により確認します。
現況届の提出が必要な方には6月中に現況届を郵送します。提出期限までに提出してください。
現況届が必要な方
- 離婚協議中で配偶者と別居または世帯分離をしている方
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出の際に、子が無職・その他と記載した方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の住民票がない方
- 法人である未成年後見人
- 施設・里親の受給者
- その他、公簿等により受給者及び児童の状況が確認できない方
-
手続の検索・電子申請(マイナポータル)(外部リンク)

現況届については、お手元にご案内が届いた後、電子申請も可能です。
詳しくは、郵送で届くご案内をご覧ください。
所得逆転による受給者の切替を希望される方へ
児童手当は、8月分~翌年7月分が「1年度」です。
所得逆転により、母と父で受給者の切替を希望される方は、8月分から切替が可能です。
8月分から切り替えるためには、7月中に新受給者の認定請求書を提出してください。
※令和7年8月分~令和8年7月分の児童手当については、令和6年中所得を審査します。
-
認定請求書 (PDF 357.2 KB)

※A4両面で印刷してください。 -
認定請求書記入例 (PDF 527.0 KB)

認定請求書の記入例です。 -
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 112.5 KB)

※子が3人以上かつ大学生年代の子がいる方のみ提出をお願いします。 -
監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例 (PDF 206.5 KB)

※監護相当・生計費の負担についての確認書の記入例です。
次のような場合は届出を
届出がないと、手当の支給ができなくなる場合があります。
また、届出が遅れると手当を返還していただく場合があります。
- 申請者が公務員になったとき
- 申請者と児童が別居となるとき
- 振込口座を解約、変更するとき(申請者名義以外の口座には変更できません)
- 申請者の所得額、控除額等を修正したとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育する方のみ)
- 児童が施設等に入所または入院したとき
- 児童または申請者が拘禁となったとき
- 児童または申請者が死亡したとき
- 特別な理由なしに、生活の本拠が住民登録地とは別の住所にあるとき
- その他、申請時から変更があったときや、支給要件に該当しなくなったとき
児童手当の受給資格について、関係書類の提出を求める場合があります。
正当な理由なく調査に応じないときは、手当の支給ができなくなります。
-
手続の検索・電子申請(マイナポータル)(外部リンク)

認定請求、額改定、現況届の電子申請はこちらから
児童手当の口座を変更したい方へ
児童手当の口座を変更したい場合は、振込日の1か月前までに口座変更届と変更後口座情報のコピーを郵送してください。
※受給者の名義の口座のみ変更可能です。(配偶者や子の口座に変更はできません。)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども未来部子育て支援課手当・助成係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1761) ファクス:042-563-5928
子ども未来部子育て支援課手当・助成係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。