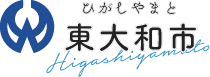国民健康保険税について
国民健康保険税額
算定方法
国民健康保険税(保険税)は、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(支援金分)及び介護納付金課税額(介護分)の三つの課税区分の合計額で、それぞれ所得割額と均等割額の二方式で算定しています。
<令和7年度の保険税>
医療分
- 所得割額:[前年の総所得金額等(※1)-基礎控除(430,000円(※2))]×7.42%
- 均等割額:37,200円×国保加入者数
年税額=所得割額+均等割額(課税限度額66万円)
支援金分
- 所得割額:[前年の総所得金額等(※1)-基礎控除(430,000円(※2))]×2.50%
- 均等割額:12,300円×国保加入者数
年税額=所得割額+均等割額(課税限度額26万円)
介護分
介護分は、40歳以上65歳未満の加入者が該当になります。
- 所得割額:[前年の総所得金額等(※1)-基礎控除(430,000円(※2))]×2.45%
- 均等割額:14,100円×国保加入者数
年税額=所得割額+均等割額(課税限度額17万円)
- ※1「前年の総所得金額等」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額をいいます。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)
- ※2 基礎控除額
- 合計所得金額2,400万円以下:43万円
- 合計所得金額2,400万円超2,450万円以下:29万円
- 合計所得金額2,450万円超2,500万円以下:15万円
- 合計所得金額2,500万円超:0円(適用なし)
- ※保険税と住民税との違い:保険税は、所得税や住民税とは異なり、基礎控除以外の所得控除(扶養、配偶者、社会保険料、生命保険料など)は適用されません。
国民健康保険税額の試算(目安)
世帯主(国保に加入していない場合であっても軽減の試算に必要)及び国保加入者の前年の給与収入等を基に、令和7年度の国民健康保険税額の試算(目安)をすることができます。
詳細につきましては、以下のページをご覧ください。
納税義務者
国民健康保険制度では、保険税の納税義務者は世帯主になります。
世帯主が社会保険や後期高齢者医療制度に加入されている場合であっても、ご家族が国民健康保険に加入されている場合は、『擬制世帯主』として世帯主に保険税の納税義務が生じます。課税額は国民健康保険に加入している方の分のみです。
納税通知書
- 保険税は世帯ごとに計算します。
- 世帯内の国保加入者全員分について算定した税額を世帯主の方(納税義務者)宛てに送付します。
- 保険税の納税通知書は、原則、7月に、1年間分(4月から翌年の3月まで)をまとめて送付します。
- 年度途中の加入の場合は、原則、届出月の翌月に、加入月から翌年3月分までの月数で算定した納税通知書を送付します。但し、4月、5月、6月の届出分につきましては、原則7月に納税通知書を送付します。
- 年度途中に加入者の増減や総所得金額等の変更があった世帯は、その都度、保険税を再計算します。再計算した結果、税額に変更が生じる場合は、税額変更後の納税通知書を改めて送付します。
※納税通知書と納付書は、分冊式となっていますので、ご注意ください。
納付
普通徴収(納付書及び口座振替)
| 納期 | 納付月 |
|---|---|
| 第1期 | 7月 |
| 第2期 | 8月 |
| 第3期 | 9月 |
| 第4期 | 10月 |
| 第5期 | 11月 |
| 第6期 | 12月 |
| 第7期 | 1月 |
| 第8期 | 2月 |
- 注1:各期別とも月末が納期限となります。ただし、12月納期は、25日が納期限となります。
- 注2:月末及び12月25日が土曜日又は休日に当たる場合は、休日の翌日が納期限となります。
- 注3:東大和市では、1年間の保険税額を最大8回の期別に分けて課税します。そのため、納付月(納期限が設定されている月)と算定対象月(保険税の算定対象となっている月)は、必ずしも一致しません。
- 保険税の納付に際し、手続が簡単な口座振替をご利用ください。納付方法を口座振替に変更する手続をされますと、自動的に指定の口座から保険税を納付することができます。納付のために足を運ぶ必要や、納付が遅延し延滞金が発生するようなリスクも軽減されるため、大変便利です。国民健康保険は加入者みんなで支えあう地域医療保険であるため、納期内の納付にご協力ください。
保険税の特別徴収(年金からの差し引き)
次の(ア)~(エ)の4つの条件全てに該当する世帯は、保険税の特別徴収(年金からの差し引きによる納付)となります。特別徴収の対象となると、世帯主の年金(介護保険料が特別徴収されている老齢基礎年金等)から、世帯分の保険税が差し引かれます。
|
条件 |
内容 |
|---|---|
| (ア) | 世帯主が国保に加入している。 |
| (イ) |
世帯内の国保加入者全員が、65歳以上75歳未満である。 (年度中に75歳に到達する方がいる世帯を除く。) |
| (ウ) | 世帯の特別徴収の対象となる年金(介護保険料が特別徴収されている老齢基礎年金等)が年額18万円以上である。 |
| (エ) | 保険税と介護保険料の1回当たりの特別徴収額の合計が、1回当たりの年金支払額(上記(ウ)の年金における支払額)の2分の1を超えない。 |
特別徴収の納付時期
4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回の特別徴収となります。4月、6月、8月分については、当該年度の保険税(年税額)が確定していないため、仮徴収という方法で特別徴収します。
仮徴収額
前年度の2月に特別徴収により保険税を納付されている方の仮徴収額:前年度の2月の特別徴収額と同額
新たに特別徴収の対象になる方の仮徴収額:原則、前年度の保険税(年税額)を6分割した金額
特別徴収から口座振替への変更
<特別徴収に該当する条件>を満たしている場合、納付方法は自動的に特別徴収となりますが、届出により、保険税の納付方法を、特別徴収から口座振替に変更することができます。
保険税の納付方法の変更を希望される方は、以下の「納付方法の変更手続に必要なもの」をご持参の上、保険年金課(市役所1階2番窓口)でお手続ください。
|
納付方法の変更手続に必要なもの |
|---|
| (1)公的機関が発行した顔写真付の証明書(マイナンバーカード、運転免許証等) |
| (2)金融機関等の口座番号等がわかるもの |
| (3)口座届出印 |
〔留意点〕
- 選択できる納付方法は「口座振替」のみになります。「納付書払い」への変更は選択できません。
- 保険税に滞納のない方のみ、納付方法の変更が可能です。
- 納付方法が特別徴収から口座振替に切り替わる時期について、直近の年金支給月分の特別徴収から変更とならない場合があります。(市から日本年金機構へ特別徴収の中止を依頼した後、日本年金機構で特別徴収を中止するまでに時間を要するため。)
- 納付方法を口座振替から特別徴収に戻したい場合は、再度お手続が必要となります。
所得申告
- 保険税は、市・都民税と同じく、被保険者の申告に基づいて算定いたします。年末調整を受けた方以外は、税務署へ確定申告されるか、市役所に市・都民税の申告をする必要があります。
- 所得が少ない方については、所得の申告をすることで、保険税が軽減される場合や、高額療療費の支給条件が有利になる場合があります。ただし、適用には世帯主及び国保加入者全員の所得の申告(年末調整、確定申告、市・都民税の申告)が必要となりますので、収入が少ない場合や、収入がない場合でも必ず申告をしてください(扶養親族以外の高齢の方でも申告の義務があります)。
軽減・減免制度
以下の要件に該当する世帯は、保険税の軽減・減免が適用される場合があります。
7・5・2割軽減
7割軽減
均等割額の7割分が減額されます。
- 要件
前年の世帯の総所得金額が「430,000円+(給与所得者等の数-1)×100,000円」以下の世帯 - 減額適用後の均等割額
- 医療分…1人当たり11,160円
- 支援金分…1人当たり3,690円
- 介護分…1人当たり4,230円
5割軽減
均等割額の5割分が減額されます。
- 要件
前年の世帯の総所得金額が「430,000円+(給与所得者等の数-1)×100,000円+(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)×305,000円」以下の世帯 - 減額適用後の均等割額
- 医療分…1人当たり18,600円
- 支援金分…1人当たり6,150円
- 介護分…1人当たり7,050円
2割軽減
均等割額の2割分が減額されます。
- 要件
前年の世帯の総所得金額が「430,000円+(給与所得者等の数-1)×100,000円+(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)×560,000円」以下の世帯 - 減額適用後の均等割額
- 医療分…1人当たり29,760円
- 支援金分…1人当たり9,840円
- 介護分…1人当たり11,280円
[注意事項]
- ※軽減の適用には、世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保加入者全員の所得の申告(年末調整、確定申告、市・都民税の申告)が必要となります。
- ※給与所得者等とは、一定の給与所得(給与収入が55万円超)と公的年金等に係る所得(年金収入が65歳未満は60万円超、65歳以上は110万円超)を有する世帯主(擬制世帯主を含む)、国保加入者及び特定同一世帯所属者の方です。
- ※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、移行後も継続して同一の世帯に属する方です。ただし、世帯主が変更となった場合や、その世帯の世帯員ではなくなった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
- ※65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、公的年金等の所得金額から15万円を控除した額を、軽減判定の対象として計算します。
- ※青色専従者給与額は、軽減判定所得において、事業主の所得金額とします。
- ※申請は不要です。
未就学児軽減
国保加入者のうち、未就学児がいる場合は、対象の未就学児の均等割額(医療分及び支援金分)が半額となります。
非自発的失業者に係る保険税の軽減
倒産、解雇等で職を失った非自発的失業者であり、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」の離職理由(番号)が特定受給資格者(11,12,21,22,31,32)及び特定理由離職者(23,33,34)の場合には、離職日の翌日の属する年度からその翌年度末までの間、前年の所得の給与所得を100分の30とみなして算定し、負担軽減を行います。ただし、離職時点で65歳未満の方に限ります。
軽減を受けるには申請が必要となります。「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」を持参の上、保険年金課の窓口にてご申請をお願いいたします。
産前産後期間に係る保険税の軽減
出産の予定がある又は出産した国保加入者について、対象者の産前産後期間相当分の保険税が軽減されます。
〈産前産後期間〉
- 単胎妊娠の方:出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月の計4か月間
- 多胎妊娠の方:出産予定月(又は出産月)の3か月前から出産予定月(又は出産月)の翌々月の計6か月間
軽減を受けるには原則、届出が必要となります。
必要書類及び制度の詳細につきましては、以下のページをご覧ください。
生活困窮者等減免
生活困窮減免
災害その他特別な事情により、その利用し得る資産、能力の活用を図ったにもかかわらず、生活困窮の状態にあると認められる場合に限り、保険税の減免を受けられる場合があります。
<減免事由>
- 納税義務者又は世帯員(被保険者である世帯員をいう。以下同じ。)が死亡し、疾病にかかり若しくは負傷したこと又は国民年金法等に定める1級程度の障害を負ったことにより世帯(納税義務者及び被保険者である世帯員で構成される世帯をいう。以下同じ。)の収入が著しく減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により世帯の収入が著しく減少したとき。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により世帯の資産に重大なる損害を受けたとき。
- 1~3までの事由に類する事由がある場合で、市長が特に必要と認めるとき。
※納期限がすでに到来している保険税は、減免の対象となりません。減免を希望される場合は、事前に窓口等で相談の上、納期限までに申請する必要があります。
生活保護受給者に係る減免
生活保護法の規定による保護を受けることとなった場合に、減免申請の日以後に到来する納期に係る保険税について、減免の対象となります。納期限を過ぎた保険税は、減免の対象になりません。
刑事施設等に収監された方の減免
国民健康保険法第59条に定める施設(刑事施設等)に収監された場合に、その収監された期間における保険税について、減免の対象となります。入所中又は退所後に、減免申請が必要となります。
後期高齢者医療制度への移行に伴う保険税の軽減
75歳になりますと、現在加入している健康保険から後期高齢者医療制度に移行します。例えば、夫が後期高齢者医療制度に移行し、妻が引き続き国保に加入する場合や、妻が夫の社会保険の扶養から外れ、国保に加入する場合、世帯の保険税が急激に増加し、負担とならないよう、以下の措置がとられています。
既に国民健康保険に加入している方へ
均等割額の軽減
均等割額の軽減が適用されている世帯において、75歳に到達する方が後期高齢者医療制度に移行することにより、世帯内の国保加入者数が減少しても、従前と同様の減額措置を受けることができます。
5割軽減
前年の世帯の総所得金額が「430,000円+(給与所得者等の数-1)×100,000円+(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)×305,000円」以下の世帯
2割軽減
前年の世帯の総所得金額が「430,000円+(給与所得者等の数-1)×100,000円+(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)×560,000円」以下の世帯
社会保険等から国民健康保険に加入した方へ
旧被扶養者の保険税の減免
社会保険等の本人であった方が後期高齢者医療制度に移行することにより被扶養者であった方が国保に加入することになります。従来、扶養家族の方が65歳以上の場合(旧被扶養者といいます)、ご申請いただくことにより、当分の間、負担を軽減するため次の措置を受けることができます。
- 国保に加入された「旧被扶養者」の方の所得割額は、課税されません。
- 国保に加入された「旧被扶養者」の方の均等割額は、半額となります。(資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限ります。)
※この措置の適用には申請が必要です。また、低所得者世帯にかかる均等割額の7割軽減、5割軽減が適用されている場合は、均等割額の半額以上が減額されるため、2についての適用はありません。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部保険年金課国民健康保険税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1021・1023) ファクス:042-563-5927
健幸福祉部保険年金課国民健康保険税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。