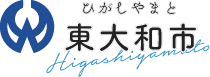保育施設の入園手続き
はじめに
- このページにおいて、「保育施設」とは、認可保育園(保育所)・認定こども園(保育部分)・小規模保育・家庭的保育を言います。また、「入園・入所」とは、保育施設に入ることを言います。このページでは、主に「入園」という言葉を使っています。
- 市内には、認可保育園17施設(分園3施設)、認定こども園2施設、小規模保育5施設、家庭的保育2施設の保育施設があります。
- 市内の保育施設については、「市内保育施設一覧」でご確認ください。
- 保育施設への入園を希望される場合は、市役所で申請してください。
(幼稚園・認定こども園(教育部分)への入園を希望される場合は、原則として各施設での申請となります。)
※入園申請される場合は、必ず申請年度の入園案内をお読みください。
入園案内や申請書類等のダウンロードページ
お知らせ
市立狭山保育園につきましては、令和4年度から令和8年度にかけ、毎年度最少年齢クラスの受入れを停止していき、令和4年度1歳児クラスが卒園となる令和8年度末をもって廃園とする段階的廃園を行います。
参考資料
入園の申請ができる方
保護者(父と母)が、次の1から8までのいずれかの事項に該当し、お子さんの保育にあたれない(保育を必要とする理由がある)場合に、入園の申請をすることができます。
※集団生活を体験させたいなどの理由だけでは、入園の対象になりません。

- 労働の場合(1か月あたり48時間以上就労している場合です)
- 妊娠・出産の場合(出産予定月を挟んで前後2か月の合計5か月以内の場合です)
- 疾病の場合(疾病のため入院、通院、居宅内療養をしている場合です)
- 障害のある場合(身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~4度の障害を有する場合です)
- 介護等の場合(介護を要する又は長期入院等をしている親族の介護をしている場合です)
- 災害の復旧にあたっている場合
- 就学等の場合(1か月あたり48時間以上の就学又は就労の技能取得ををしている場合です)
- 求職活動の場合(入園後60日を経過する日の属する月の末日までに就労することが必要です)
入園申請の受付
受付期間
一部の月(※)を除き、入園希望月の前月1日から10日までが通常の受付期間となります。
日曜日、祝日にあたる場合は、その直後の平日までとなります。
(※)4月入園は例年、受付期間が通常の期間と大きく異なります。その他の月の入園においても、連休等の影響で、通常の受付期間と異なる場合があります。必ず各年度の入園案内で受付期間をご確認ください。
申請方法
令和8年度4月一次・二次申請は、郵送(簡易書留等)、窓口、電子申請での受付となります。
詳細は、入園案内をご確認ください。
| 申請区分 | 申請方法 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 令和8年4月入園一次・二次申請 | 郵送・窓口・電子申請 |
|
|
令和7年5月~令和8年3月入園分 |
窓口・電子申請 |
|
- ※郵送遅延、宛先の誤り等、郵便事故の責任は負いかねます。簡易書留等追跡可能な方法で郵送してください。
- ※書類不備や不足等を申請期間内に訂正いただけない場合、利用調整ができない場合があります。提出前に不備がないか必ず確認してください。
- ※マイナポータルのぴったりサービスで電子申請ができます。
- ※ぴったりサービスの利用による電子申請を行う場合には、マイナンバーカード及びパスワードが必要となります。
東大和市民で他市区町村の保育施設に入園を希望する場合
他市区町村の保育施設に入園を希望する場合でも、原則、申請の受付場所は東大和市保育課となります。
この場合、東大和市が受け付けた申請書等を、入園を希望する保育施設所在の市区町村に送付することとなりますので、事前に保育施設所在地の市区町村にて締切日や必要書類、申請条件をご確認のうえ、余裕を持って申請してください。(締切日の1週間前を目安に申請してください)
※電子申請では申込できません。
市外在住で東大和市の保育施設に入園を希望する場合
市外在住の方については、次のとおり入園申請に対して制限をさせていただきます。
- 認可保育園・小規模保育・家庭的保育:0~3歳児クラスは申請不可、4~5歳児クラスは東大和市内で勤務している方のみ申請可能(ただし、4月入園2次申請以降)
- 認定こども園(保育部分):クラス年齢にかかわらず申請可能(ただし、4月入園2次申請以降。4月先行申請は可能)
なお、東大和市へ転入予定のある方については、「転入誓約書」と併せて、「売買契約書」「賃貸借契約書」などの写しを添付し、入園希望月の1日までに転入予定であることが確認できる場合には、東大和市民とみなし、上記の制限はございません。
申請の受付窓口はお住まいの市区町村となります。提出された書類は東大和市に送付されますので、東大和市の締切日に間に合うよう、余裕をもって申請してください。
※電子申請では申込できません。
申請に必要な書類
1.施設型給付費・地域型保育給付費支給認定 兼 保育利用申請書
2.同意書/重要事項確認書
※同意書の記入にあたっては、住民票の記載にかかわらず、同一住所に同居している18歳以上の方全員(同住所別世帯員をも含む)が、それぞれ署名をお願いします。
3.保育を必要とする理由が確認できる書類
保護者(父母)2人分の書類が必要です。なお、3か月以内の日付のものをご用意ください。
- 現在育児休業取得中の場合は、「育児休業の延長について」の提出が必要です。また、内定中の場合は、入園することを前提とした勤務内容(日数、時間)での就労証明書を提出された場合、その勤務内容で指数付けします。申請時の勤務内容と異なる勤務内容で復職した場合、入園取消や退園となることがあります。
- 未婚かつ未成年の場合は、入園申請に対する祖父母の同意書も必要です。同意書/重要事項確認書とは別の様式になる為、該当される方は保育課へお問合せください。
- 就学予定の場合は、在学証明書の代わりに合格通知書のコピーなどを提出してください。後日、就学が開始となりましたら、必ず在学証明書を提出してください。
| 保育を必要とする理由 | 提出書類 |
|---|---|
| 労働の場合:会社勤務 | 就労証明書 ※(入園希望月時点での契約内容が記載されたもの) |
| 労働の場合:自営業 (代表者) |
|
| 労働の場合:自営業 (親族が代表者の会社に勤務) |
|
| 妊娠・出産の場合 | 母子健康手帳(表紙及び分娩予定日の分かるページのコピー) |
| 疾病の場合 | 医師の診断書等(お子さんを保育できないことがわかるもの) |
| 障害のある場合 | 身体障害者手帳(コピー) 愛の手帳(コピー) |
| 介護の場合 | 介護を必要とする親族に係る医師の診断書等(同居していない親族の場合、要介護3~5と確認できる書類も必要です) |
| 災害復旧の場合 | 罹災証明書等 |
| ひとり親家庭の場合 | 離婚・非婚の方:戸籍(全部事項証明)等 ※ 離婚調停中の方:離婚調停・離婚裁判関係の書類のコピー及びひとり親であることの申立書 |
| 就学の場合 | 在学証明書等及び時間割のわかる書類 ※ |
| 求職の場合 | 求職活動申告書 |
4.マイナンバー(個人番号)申告書
申告書と併せて、申請保護者のうち、父母のいずれか一方の「マイナンバー(個人番号)確認書類」及び「本人確認書類」が必要です。
郵送の場合はコピーを同封してください。
| 確認事項 | 必要書類 |
|---|---|
| 個人番号確認 |
|
| 本人確認 一点で可(顔写真付き身分証) |
|
| 本人確認 二点必要(顔写真なし身分証) |
|
5.その他必要な書類 要件提出書類
- お子さんに障害がある場合
- 病名・病状・集団保育が可能であること・医療行為の有無・保育にあたっての注意事項等が書かれた医師の診断書等(3か月以内の日付のもの)
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー(お持ちの場合でも、マイナンバーの導入により、情報連携可能のため省略可)
- 愛の手帳のコピー(お持ちの場合は省略不可)
- 障害者と同居している場合
- 愛の手帳のコピー(お持ちの場合は省略不可)
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書、障害基礎年金の証書のコピー(お持ちの場合でも、マイナンバーの導入により、情報連携可能のため省略可)
- 児童に疾病(手術後の経過観察も含む)や発達の遅れがある場合(※1)
病名・病状・集団保育が可能であること・医療行為の有無・保育にあたっての注意事項等が書かれた医師の診断書等(3か月以内の日付のもの)
※以下の場合は、医師の診断書等は不要です。ただし、後日、保育施設から医師の診断書等の提出を求められる場合があります。
喘息・水いぼ・アトピー性皮膚炎・乳児湿しん・皮膚のかゆみ・血管腫のうち手足のあざ程度のもの・便秘症 - 他市区町村から市内に転入してくる場合
転入誓約書と併せて、売買契約書や賃貸借契約書など転入日がわかる書類(契約者名、転居日、転入住所などの記載があり、契約したことが分かる書類のコピー) - 育児休業取得中に申請する場合
育児休業の延長について - 海外に在住していた場合
勤務先発行の給与証明等、収入を証明する書類があれば添付してください。なお、日本語以外で書かれた証明書の場合には、必ず翻訳文を添付してください。入園希望月 海外収入申告書類対象年度 令和7年4~8月入園申請 令和6年度と令和7年度の両方 令和7年9月~入園申請 令和7年度のみ
- 利用を希望する児童が、現に認証保育所又は企業主導型保育施設の認可外保育施設等を利用している場合
認可外保育施設等利用証明書
(注)障害や疾病等があるお子さんについては、医師の診断書等により集団保育が可能であることが確認できなければ、保育施設の申請をすることができません。
利用調整方法・結果
利用調整方法
入園申請があった場合、提出書類の内容をもとに、保護者(父母)それぞれの「保育を必要とする理由」を「保育の利用基準表」に当てはめ、指数化します。保護者(父母)2人分の指数を合計したものが、その世帯の「基準指数」になります。
この基準指数等の高い世帯から順に利用調整を行います。利用調整においては、希望する保育施設の空き状況等によって、入園の可否を決定します。
利用調整の結果通知
一部の月を除き、毎月16日前後に発送いたします。お手元に通知が届くまでには数日かかりますので、ご了承ください。なお、入園の可否に関わらず「教育・保育給付認定通知書」も送付いたします。
他市の保育施設を申請された方につきましては、他市の利用調整の結果が決定するまでは、結果の通知を送付をすることができません。申請されている市から利用調整の結果が届き次第、速やかに送付いたします。
入園が可能となった場合
利用が可能となった方は、保育施設にて面接等があります。日時等については、後日、利用可能となった保育施設よりご連絡いたします。また、結果は先に保育施設にお伝えするため、お手元に結果通知が届く前にご連絡がいく場合がありますので、ご了承ください。
なお、認可保育園(保育所)以外の保育施設の利用が可となった方は、別途、保育施設で契約を締結していただく必要があります。
育児休業中で入園が可能となった方は、入園月の翌月1日までに元の職場へ復職する必要があります。必ず、復職後20日以内に「復職証明書」を保育課へご提出ください。
求職中で入園が可能となった方は、入園後2か月以内に他の要件(月48時間以上の就労等)が必要です。他の要件に該当しない場合には退園となりますので、ご注意ください。
入園決定を取り下げる場合
やむを得ない理由により、入園決定を取り下げたい場合は、入園する月の前月までに「取下届」を保育課に提出してください。「取下届」は保育課窓口でも配布しています。
保育料
保育料(利用者負担額)のページは次のリンクをご覧ください。
希望する施設の利用が不可となった場合
施設の利用が不可となった場合でも、入園申請は、取り下げの手続きがない限り、申請年度中は有効です。その期間中は毎月利用調整の対象となりますので、改めて入園申請する必要はありません。なお、保育の利用を希望する期間が3月1日より前に終了している場合については、入園申請が有効となるのはその月までとなります。
入園申請を取り下げたい場合は、必ず保育課までお手続きください。
利用不可の結果通知は、最初に入園・転園申請をした月または希望保育施設の変更・追加をされた月のみ送付いたします。それ以外の月は、入園が可能な時のみ通知を送付します。
育児休業から復帰する方で、施設利用が不可となり、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の規定により育児休業を延長された方は、申請内容の変更手続きが必要となります。就労証明書をご用意いただき、速やかに保育課窓口でお手続きください。
入園申請の有効期限は年度中のみになります。待機児童となり、そのまま年度中に入園ができなかった方で、来年度も入園を希望される場合は、再度、新たに来年度の入園申請をしていただきますようお願いします。
認可外保育施設等の利用
認可外保育施設利用者に対する補助制度
認証保育所
認証保育所を利用する場合は、保護者と認証保育所との間で入園の手続きを直接行っていただきます。また、保育料については認証保育所が定める料金となります。
東大和保育園(東大和市新堀1-1435-33、電話:042-562-1758)
対象年齢:生後57日~3歳児未満の児童受入可能
※利用申込みについては、園までご連絡ください
ベビーシッターなど
ベビーシッターなどの利用をご検討する際は、国の示す「ベビーシッターなどを利用するときの留意点(厚生労働省ホームページ)」をご参考ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども未来部保育課保育・幼稚園係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1751) ファクス:042-563-5928
子ども未来部保育課保育・幼稚園係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。